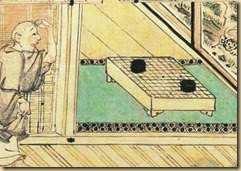前回の話題の続きを記しておく。まずは、おなじく言葉についてだが、英語表現にみるいささかな不思議がある。それは、学問分野としての映画についての研究のことを、なぜか「ムービ」研究とは言わず、「フィルム」研究と呼ぶ。きっとなにかの理由があるに違いないが、自分の中では、「能」と「謡曲」との使い分けのようなものだと勝手に解釈しているが、いつか確かめておきたい。
ここにフィルムを持ち出したのも、先週のゲームをテーマにした集まりに関連している。集まりの主催者は研究機関だということで、発表者となるとゲームを対象にした研究者が圧倒的だった。ゲームを実際に創作する人もいたが、あきらかに少数派に属する。ゲームという、まだまだ娯楽の一つとしての新参もので、変化もはなはだ激しいのに、はたして研究の対象となりうるのか、正直内心かなり疑問をもっていたものだった。そのようなわたしの目に映ったのは、多くの研究者がまるで正統な映画研究の手法を意識して踏襲したかのように、映画を語るがごとくゲームに立ち向かったものだった。いわば、ゲームの表現方法、ゲームの世界観、ゲームをまつわる社会現象や文化認識、などなど。はたしてゲームがそこまで文化的な意味合いを荷負うだけの完成度を持っているのだろうか。プレーヤーを惹きつける力だけあげてみれば、小説の読者や映画の観客と比較しても引けを取らないことはよく承知してはいるのだが。
以上の思い、とりわけ映画研究の方法論への自覚の有無について、一人の研究者に思い切ってぶつけてみた。意外な答えが戻ってきた。いわく、その方の研究意識においては、ゲームというものはいかにして映画と違うのかということへの追求が最大のテーマなのだ、とか。どうやら素朴な問いは、当たらなくても遠く外れてはいない。ゲームをめぐる文化的な視線としての、現時点の一つの立ち位置として、記憶に値するかもしれない。