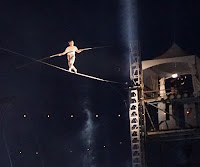Googleメールボックスで広告のフォルダに自動的に振り分けられたメールのタイトルを眺めたら、Audibleからの一か月無料体験の誘いがあった。音楽ではなく、時事や朗読などをBGMのつもりで聞いている身としては、これを良いことにサービス利用を再開した。
個人アカウントに入ったら、これを一年ほど利用してから、二年前ほどに停止を選んだ。時間がずいぶん経ったのに、アマゾンへのアクセスのパスワードは変わらず、サイトに保存された個人情報も、支払い方法も、そして利用期間中に購入したタイトルもすべてそのままなのだ。一方では、あのころコインで決まったタイトル数だけ利用するというシステムが廃止され、代わりに会員となる期間中には聞き放題、会員を止めたらタイトルへのアクセスは無効、言い換えれば会員の料金はあくまでもコンテンツの利用であり、個人所有はタイトルの個別購入に限るという、分かりやすいと言えば分かりやすい方針に転換された。サイトの宣伝によれば、12万以上のタイトルが収録されているとされる。しかしながら、よく眺めてみると、時の流れと連動するタイトルはいまでもかなり限られている。フィクションの分類の、ほとんど最初のページから昔の名作、いわゆる著作権が切れた作品が登場してしまう。いまを時めく作品の音声化は、まだ理解されていないんだと感じさせる。二年前に利用を停止した理由も、たしかにここにあったのだと思い出された。