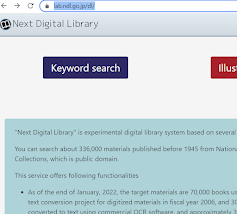今週伝わってきたニュースの一つには、京都大学貴重資料デジタルアーカイブが同図書館所蔵の大惣本の一部をデジタル公開したというのがある。公開したのは417タイトル、全所蔵の3667部のわずか一割強にすぎないが、纏まりのある公開は、やはりインパクトがある。
公開の方法は、IIIFに基づき、安心してアクセスできる。一方では、中身や分量に対して、いまだ検索などの対応が十分に整っていない。デジタル制作について、「国文学研究資料館が実施する「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」(略称:歴史的典籍NW事業)に拠点大学として参加して実施し」た結果だと明示し、個々の書誌データも「日本古典籍総合目録データベース(国文学研究資料館作成)による」と記すが、これに対して、新日本古典籍総合データベースの方から今度公開のタイトルを検索すると、大惣本との記述があるが、画像へのリンクがまだ用意されていない。現時点では、デジタル公開されている『京都大学蔵大学蔵目録』(三冊)を頼りに、同デジタルアーカイブの検索機能で狙いのタイトルにたどり着くか、18に及ぶ「書誌一覧」の画面を順に眺めるほかはない。思えば、「大惣本」という言葉は、たしかに「貸本屋」と同時に覚えたものだった。大学院生のころ、近世を専門とする同級生が興奮した口ぶりでこれを説明し、目録作成に参加するように熱心に誘ってくれたのだった。ただ、新しい分野の勉強を始める余裕がとてもなくて、羨ましい目で作業に取り組む姿を側から眺めていた。あれから四十年近くも時間が経った。いまは世界のどこにいても同じ書物を開くことができるようになったと、感無量だ。