今週、日本の古典研究に携わる人々の中でさかんに交わされた話題の一つには、ニューヨークのメトロポリタン美術館が去年主催の源氏物語特別展の図録を無料公開したというのがあった。特別展のタイトルは、「The Tale of Genji: A Japanese Classic Illuminated」(源氏物語:飾られた日本の古典)、展示物の内容は、判読できる程度のデジタル画像ですでに公開されている。それに加えて、展覧会の図録は、かなり鮮明な画像を含むPDFファイルでクリック一つで入手できるようになった。366ページにも及び、印刷媒体の販売価額は70ドルだという、じつに豪華ものだ。
 同美術館公式サイトの「出版物」の項目に収録されたこの貴重な一冊をダウンロードしながら、自然とこれまでも日本関連の特別展の様子、図録の公開などを見てまわった。半世紀もまえまでに遡り、簡単に見ていても、図録は今度の公開を含めて七つと数えられる。その概要は、「マリー&ジャクソンボークコレクション」(1975)、「漆器」(1980)、「不老不死」(1993)、「夢の浮き橋」(2000)、「十六世紀の美」(2003)、「物語絵」(2011)、「源氏物語」(2019)である。ここまで頻繁に日本を取り上げ、しかも丁寧にまとめた図録を惜しみなく、分かりやすい形で公開していることには、やはり頭が下がる思いでいっぱいだ。
同美術館公式サイトの「出版物」の項目に収録されたこの貴重な一冊をダウンロードしながら、自然とこれまでも日本関連の特別展の様子、図録の公開などを見てまわった。半世紀もまえまでに遡り、簡単に見ていても、図録は今度の公開を含めて七つと数えられる。その概要は、「マリー&ジャクソンボークコレクション」(1975)、「漆器」(1980)、「不老不死」(1993)、「夢の浮き橋」(2000)、「十六世紀の美」(2003)、「物語絵」(2011)、「源氏物語」(2019)である。ここまで頻繁に日本を取り上げ、しかも丁寧にまとめた図録を惜しみなく、分かりやすい形で公開していることには、やはり頭が下がる思いでいっぱいだ。
特別展の図録は、鑑賞にしても研究にしても貴重な価値があり、しかも普通の書籍とは違う流通経路をもつことから、簡単に入手できない部類の資料に入る。日本の美術館などを訪ねると、過去の特別展の図録を買い求めることは、いつも大きな楽しみの一つだ。日本の場合、あるいは図録のデジタル無料公開はとても考えられないかもしれないが、せめて有料販売でも実現できればと、ひそかに願っている。
2020年4月25日土曜日
MET図録
Labels: 展覧会へ行こう
2019年6月8日土曜日
石置板葺
学生たちと歩く日本。ホスト校にほど近い「日本民家園」は毎回一度訪れる。広大な緑地の中に展開し、実物大の古家屋が軒を列なる様子は、ほかでは見かけられない風景を成していて、眺めていてとても見ごたえがある。
 園内に入ってすぐの宿場エリアの最後に位置するのは、長野県にあった三澤家だ。建物の特徴的なことの一つには、その屋根の造りがある。周りの茅葺きや瓦葺きのものと違って、屋根の上にかなりの密度をもって置かれたのは、なんの変哲もない石ころである。じつは、これを見るたびに思い出すのは、あの絵巻「長谷雄草紙」に描かれた一場面だった。間違いなく同じような姿の屋根を街角の様子として描きこまれたものだった。初めてあの場面を眺めたころ、関連の知識を持たないまま、ずいぶんと戸惑ったことをいまでも覚えている。それをまるでタイムスリップのように、絵と現実の建物とが目の前でつながっていることには、やはり感慨深いものがあった。
園内に入ってすぐの宿場エリアの最後に位置するのは、長野県にあった三澤家だ。建物の特徴的なことの一つには、その屋根の造りがある。周りの茅葺きや瓦葺きのものと違って、屋根の上にかなりの密度をもって置かれたのは、なんの変哲もない石ころである。じつは、これを見るたびに思い出すのは、あの絵巻「長谷雄草紙」に描かれた一場面だった。間違いなく同じような姿の屋根を街角の様子として描きこまれたものだった。初めてあの場面を眺めたころ、関連の知識を持たないまま、ずいぶんと戸惑ったことをいまでも覚えている。それをまるでタイムスリップのように、絵と現実の建物とが目の前でつながっていることには、やはり感慨深いものがあった。
説明の案内には、「石置板葺の屋根」とある。あまりにも明快で、いかにも第三者的な立場からの正確を期する解釈調のネーミングだ。当時の人々、自分の住んでいるうちや、これを建てた大工さんたちなら、これをどのように呼び指していたのだろうか。慎重に探すべき課題の一つだ。
Labels: 展覧会へ行こう
2019年2月23日土曜日
平等院参詣図
火曜の午後、短い関西への旅から戻ってきた。あわせて四泊六日の、相変わらずの詰まった日程だった。それでも、あるいはそれだから余計に積極的に動き回った。中でも、かねてから思いに掛けてきた平等院を訪ねた。学生時代以来、かなり久しぶりの再訪だった。五年ほど前に修復が終わり、本堂の色が一新されたとの噂を聞いたから、その変化ぶりもぜひこの目で見たかった。
 ミュージアム鳳翔館と名乗る宝物殿は、出来てすでに二十年近く経っているらしい。国宝・雲中供養菩薩像の展示ホール、実物大の本堂の扉など、さすがに圧倒される。時に冬期企画展が開催されている。展示の中では、「平等院参詣図」(江戸時代前期)はとりわけ印象深い。参詣の対象となる平等院、そしてそれに投げかけられた普通の人々の姿などは、じっと眺めていて興味が尽きない。普段はどうやら拝観者を本堂に入れないらしく、神社の拝殿に向えるのと同じく、熱心な男は扉の格子に顔をいっぱいくっつけたまま中を覗く。建物全体を見れば、特徴となる渡り橋が見当たらないことには驚いた。ただ、その目で見れば、そもそも宇治川が本堂のすぐ後に迫ってきているのだから、絵画的な表現を考慮に入れて見るべきだとはっと思い返させられた。
ミュージアム鳳翔館と名乗る宝物殿は、出来てすでに二十年近く経っているらしい。国宝・雲中供養菩薩像の展示ホール、実物大の本堂の扉など、さすがに圧倒される。時に冬期企画展が開催されている。展示の中では、「平等院参詣図」(江戸時代前期)はとりわけ印象深い。参詣の対象となる平等院、そしてそれに投げかけられた普通の人々の姿などは、じっと眺めていて興味が尽きない。普段はどうやら拝観者を本堂に入れないらしく、神社の拝殿に向えるのと同じく、熱心な男は扉の格子に顔をいっぱいくっつけたまま中を覗く。建物全体を見れば、特徴となる渡り橋が見当たらないことには驚いた。ただ、その目で見れば、そもそも宇治川が本堂のすぐ後に迫ってきているのだから、絵画的な表現を考慮に入れて見るべきだとはっと思い返させられた。
しかしながら、本堂の象徴となる屋根の上の鳳凰は、それぞれ違う方向に頭を向かわせている。江戸時代以後、鳳凰の向きを調整したとはとても考えられない。ならば、そこまで現実を無視して描いた参詣図の意図とは、どのようなところに託されたのだろうか。課題の一つとしたい。
Labels: 展覧会へ行こう
2019年2月19日火曜日
天皇即位の図
 二日にわたる研究会が終了したあと、京都博物館に駆けつけ、閉館までのわずかな時間をねらって展示を楽しんだ。つぎの特別展は二か月先、いわば主役不在の時期ではあるが、それでも見ごたえのものが多かった。なかでも特筆すべきなのは、やはりいまは世の中の関心があつまる改元即位にまつわる小規模ながらの特別企画である。
二日にわたる研究会が終了したあと、京都博物館に駆けつけ、閉館までのわずかな時間をねらって展示を楽しんだ。つぎの特別展は二か月先、いわば主役不在の時期ではあるが、それでも見ごたえのものが多かった。なかでも特筆すべきなのは、やはりいまは世の中の関心があつまる改元即位にまつわる小規模ながらの特別企画である。
展示ホールの中心を鎮座するのは、「霊元天皇即位・後西天皇譲位図屏風」である。絵師は、あの「本朝画史」を著述したことで有名な、狩野家三代当主の狩野永納である。屏風は今回初公開となる。譲位、即位の詳細、画面内容の記述などをめぐる詳細な解説は、きれいな写真が添えられて無料で配布されている。二隻の屏風は、右隻は即位、左隻は譲位と構成され、とりわけ当時十歳の霊元天皇は、顔が正面から明晰に描かれていて、同様題材の屏風の中でも特異だと指摘されている。同時に展示されたものには、同屏風の摸本があった。こちらは白い紙に墨線で構図を慎重に描き写したのみに止まり、ただ文字の転写はかなり正確であり、一部今日になっては判読しづらい文字の内容を伝えてくれているところもあると、解説が教えてくれている。天皇の譲位、即位という一大国家行事をめぐる人々の視線、とりわけ敬いや憧れの念を抱きながらこれを記録し、そして描き写して手元に残すという姿勢が伺え、完成度のまったく異なる二つの資料が並べられて、得難い鑑賞経験となった。同展示はあと三週間ほど残っている。一見の価値があると勧めたい。
東京博物館の常設展は写真撮影を許していることからして、国立の博物館はすべて同じ方針を取っているとばかり思いこんだ。(「ドイツ初期銅版画」、「豚を料理」)なんとそういうわけではない。京博の常設展は撮影不可となっている。自分の不明を訂正し、いつかこの状況が変わることを願う。
特集展示 初公開!天皇の即位図
Labels: 展覧会へ行こう
2018年7月7日土曜日
古書入札会
この週末、二日にわたり「七夕古書大入札会」が開催されている。すでに53回と数えるこの行事は、古本屋さんしか入札の権利がないが、普通に関心をもつ人々にも公開され、これまで数回覗いたことがある。さいわい好天に恵まれ、今度も出かけてきた。
 出発の直前になって、妙なメールが飛び込んできた。「双六ねっと」を頼りに、まったく面識のない愛好者がニューヨークから連絡を寄越し、個人所蔵の双六の写真を添付してきた。感心して入札会の目録を眺めてみれば、今年はじつは11点も出品されている。さほど注目を集めているようには見えず、一人しずかにそれを眺めることができた。自由闊達でいて、情報が豊富に詰まっているこの貴重なジャンルは、やはり魅力に満ち溢れている。表現の様式という視線で観察していても、さまざまなバリエーションがそこに開示されている。「賑式亭繁栄勝双六」は文字情報がいちばん多い。それぞれの枡に薬の名前が掲げられ、効用の説明から値段まで充実な宣伝文句が添えられる。その枡から振り出される賽の数字への指示も丁寧に記入されている。これに対して、「大日本六十余州一覧双六」は、地名とその地の有名人や風景に加えて数字の指示が見られ、「東海道五拾三駅大双陸」はつぎの枡の地名とそれまでの距離だけ掲げ、数字の指示はない。「新板七津伊呂波清書双六」となれば、舞台上のポーズに順番が振られているのみで、枡のタイトルさえ提示されていない。ただし、じっくり眺めてみれば、どれも遊びの道具として明らかに機能し、おそらくその時その場のローカルルールが案出されるのではないかと思わせるものだった。
出発の直前になって、妙なメールが飛び込んできた。「双六ねっと」を頼りに、まったく面識のない愛好者がニューヨークから連絡を寄越し、個人所蔵の双六の写真を添付してきた。感心して入札会の目録を眺めてみれば、今年はじつは11点も出品されている。さほど注目を集めているようには見えず、一人しずかにそれを眺めることができた。自由闊達でいて、情報が豊富に詰まっているこの貴重なジャンルは、やはり魅力に満ち溢れている。表現の様式という視線で観察していても、さまざまなバリエーションがそこに開示されている。「賑式亭繁栄勝双六」は文字情報がいちばん多い。それぞれの枡に薬の名前が掲げられ、効用の説明から値段まで充実な宣伝文句が添えられる。その枡から振り出される賽の数字への指示も丁寧に記入されている。これに対して、「大日本六十余州一覧双六」は、地名とその地の有名人や風景に加えて数字の指示が見られ、「東海道五拾三駅大双陸」はつぎの枡の地名とそれまでの距離だけ掲げ、数字の指示はない。「新板七津伊呂波清書双六」となれば、舞台上のポーズに順番が振られているのみで、枡のタイトルさえ提示されていない。ただし、じっくり眺めてみれば、どれも遊びの道具として明らかに機能し、おそらくその時その場のローカルルールが案出されるのではないかと思わせるものだった。
入札会の魅力は、どの出品も自由に触れられるとのことである。今年も、「大江山絵巻」(三巻)と「二十四孝」(二巻)をゆっくり披いた。素晴らしい思い出になった。
七夕古書大入札会
Labels: 展覧会へ行こう
2017年12月23日土曜日
文字の姿
今年は、曜日の並びもあって、金曜日からすでに年末年始の休暇に突入した。大学もキャンパスが完全に締まり、新年あけの二日まで休みが続く。この一年のことをあれこれと整理し、日本から持ち帰った書籍を手に取ったら、あの「絵巻マニア列伝」のカタログを読み耽け、再び惹かれた。
 たとえば右に示した二行の抜粋。おそらくこの展示全体を見渡しても一つの代表的なものであり、絵巻、それの制作、そして享受を結びつける精緻をきわめた一コマに違いない。二行の文字は、「実隆公記」に記され、「及晩石山絵詞立筆」(明応六年十月九日)、「石山縁起絵詞終書写功」(同十一日)と読む。新たに巻四を補作するにあたり、実隆は書写を依頼され、名誉ある作業を三日ほどかけて完了させたものである。あわせて六段、数えて百三十九行という分量である。それにしても、文字の姿というのは、見つめるほどに味わいがあり、想像を羽ばたたせる。「石山寺縁起」の詞書は、簡単に見られるので、関心ある人ならすでに繰り返し読んだことだろう。じつに堂々たる書風で、今日の人々が抱く中世の文字のイメージをそのまま具現化したものである。一方では、同じ人間でありながら、日記という私的なものとなると、文字はこうも違う。すべての線はおなじ太さを持ち、文字の形は思いっきり崩され、おそらく凄まじいスピードで書きあげられ、筆者以外の人への情報伝達を最初から拒んでいるようにさえ見受けられる。
たとえば右に示した二行の抜粋。おそらくこの展示全体を見渡しても一つの代表的なものであり、絵巻、それの制作、そして享受を結びつける精緻をきわめた一コマに違いない。二行の文字は、「実隆公記」に記され、「及晩石山絵詞立筆」(明応六年十月九日)、「石山縁起絵詞終書写功」(同十一日)と読む。新たに巻四を補作するにあたり、実隆は書写を依頼され、名誉ある作業を三日ほどかけて完了させたものである。あわせて六段、数えて百三十九行という分量である。それにしても、文字の姿というのは、見つめるほどに味わいがあり、想像を羽ばたたせる。「石山寺縁起」の詞書は、簡単に見られるので、関心ある人ならすでに繰り返し読んだことだろう。じつに堂々たる書風で、今日の人々が抱く中世の文字のイメージをそのまま具現化したものである。一方では、同じ人間でありながら、日記という私的なものとなると、文字はこうも違う。すべての線はおなじ太さを持ち、文字の形は思いっきり崩され、おそらく凄まじいスピードで書きあげられ、筆者以外の人への情報伝達を最初から拒んでいるようにさえ見受けられる。
絵巻と古記録、絵画と文字、そして作品とマニア、これを同列に一堂に集めた展覧会の様子は、いまでも脳裏に明晰に残っている。一方では、文字資料には、翻刻や現代語訳、ひいては音声解説など、多くの説明が施されたが、それでも見る人の足を止められなかったように見受けられた。新たなアプローチだけに、よりマッチした展示の方法とはなにか、やはりついつい空想してしまうものだった。
Labels: 展覧会へ行こう
2017年6月4日日曜日
豚を料理
大きな美術館の常設展には、さまざまなユニークな魅力を持っている。個人的にその一つは、写真撮影可能というものだ。(「展覧会で広がる”写真撮影OK”その裏側とは」)多くの資料は、すでにデジタルの形で利用できるようになったと知っていても、やはりカメラを構えてみたくなる。自分のレンズを通したら、なぜか落ち着きを覚え、作品との距離が近くなる。週末に自由の時間に恵まれ、東博を訪ねた。
 今度も、あれこれじっくりと見て回った。絵巻関連では、あの「綱絵巻」が全巻広がる形で展示されていて、人に囲まれることなく気が済むまでゆっくり見れた。国宝館には、年間の展示予定が掲げられ、あの「一遍聖絵」が九月に登場してくる予定だ。一方では、アジア館は、やはり素晴らしい。とりわけ中国の画像石の展示にはとても充実なものがあった。なかでも、料理関連の場面は、いくつも集められている。つねに関心をもつテーマであり、すっかり見入った。たとえば右に掲げる豚と、これに取り掛かる男の姿は、なんとも印象的だ。(画像石・酒宴/厨房、TJ-2030)男の右手は包丁を握り、高々と力強く振り上げられている。説明の文にあったように、料理の前段階としての、豚解体に取り掛かったところだろう。生き生きとした状況を伝えるにはシンプルな線しかないが、それが確実でいて味わい深い。画面をよくよく眺めてみれば、料理師の突き出す気味のお腹は微笑ましい。二千年前のメタボ男は、その歳と貫禄を遺憾なく今日に訴えている。
今度も、あれこれじっくりと見て回った。絵巻関連では、あの「綱絵巻」が全巻広がる形で展示されていて、人に囲まれることなく気が済むまでゆっくり見れた。国宝館には、年間の展示予定が掲げられ、あの「一遍聖絵」が九月に登場してくる予定だ。一方では、アジア館は、やはり素晴らしい。とりわけ中国の画像石の展示にはとても充実なものがあった。なかでも、料理関連の場面は、いくつも集められている。つねに関心をもつテーマであり、すっかり見入った。たとえば右に掲げる豚と、これに取り掛かる男の姿は、なんとも印象的だ。(画像石・酒宴/厨房、TJ-2030)男の右手は包丁を握り、高々と力強く振り上げられている。説明の文にあったように、料理の前段階としての、豚解体に取り掛かったところだろう。生き生きとした状況を伝えるにはシンプルな線しかないが、それが確実でいて味わい深い。画面をよくよく眺めてみれば、料理師の突き出す気味のお腹は微笑ましい。二千年前のメタボ男は、その歳と貫禄を遺憾なく今日に訴えている。
豚料理の隣に描かれたのは、天井に吊るされた魚と、酒の醸造。料理法、料理の環境、料理その行動の意味や位置付けなどもろもろの課題についてきわめて示唆が多く、語られ甲斐のあるものに違いない。ただ、誇張されたタッチで伝えられたものは、おそらく写実の対極的なところに位置するものだろう。画像が分かりやすい分、この事実を見落としたり、見逃したりすることへの警戒を忘れてはならない。
Labels: 展覧会へ行こう
2017年5月13日土曜日
蛇人間
語学研修の学生たちを連れて短い東京滞在を始めた。この春は、古典画像テーマの展示はいくつも行われている。中でも企画される段階から話を聞いていた「絵巻マニア列伝」にはずっと関心を持ち続けてきた。最初の自由時間になってさっそく駆けつけ、終了前日に滑り込みの形でじっくり鑑賞することができた。
 思いに残ったものはとても多い。ここに画面を見つめての記憶の一つを記しておきたい。近年、いささか話題になった「地蔵堂草紙絵巻」をはじめて目にした。ストーリとしては、竜宮での良い思い出が人間の世に戻ったら体全体が蛇になったという、奇想天外を滑稽談にするような、愉快なものだった。とりわけビジュアルに表現される蛇人間の姿に驚きを覚えた。かつて短く書き記したものだが、蛇になった人間といえば、頭が人間で体が蛇、あるいはその反対の体が人間で頭が蛇という二つのシナリオしか考えに上がらなかった(「人面蛇身」)。そんなところに、と三番目の構図が目の前にあった。いわば蛇に身を載せた人間で、二者が分かれられずに一体になったというものである。そもそも非日常的な様子を限られた画像空間に取り入れようとすれば、ここまで苦労が多い。
思いに残ったものはとても多い。ここに画面を見つめての記憶の一つを記しておきたい。近年、いささか話題になった「地蔵堂草紙絵巻」をはじめて目にした。ストーリとしては、竜宮での良い思い出が人間の世に戻ったら体全体が蛇になったという、奇想天外を滑稽談にするような、愉快なものだった。とりわけビジュアルに表現される蛇人間の姿に驚きを覚えた。かつて短く書き記したものだが、蛇になった人間といえば、頭が人間で体が蛇、あるいはその反対の体が人間で頭が蛇という二つのシナリオしか考えに上がらなかった(「人面蛇身」)。そんなところに、と三番目の構図が目の前にあった。いわば蛇に身を載せた人間で、二者が分かれられずに一体になったというものである。そもそも非日常的な様子を限られた画像空間に取り入れようとすれば、ここまで苦労が多い。
展示会の眼目は、いうまでもなく「マニア」という一言に尽きる。違う時代の代表格のビッグネームに焦点を絞り、貴族日記を紐解いて、読み下しと現代語訳を添えての構想は、とても魅力的だ。いっぽうでは、会場からも分かるように、普段の人々と古日記との距離は、さすがに簡単に埋められるものではない。ビジュアル資料を対象にしているだけに、ほかになにかもっと伝わるアプローチがないものかと、ついつい思いめぐらしたものだった。
絵巻マニア列伝(展示構成)
Labels: 展覧会へ行こう
2016年12月31日土曜日
絵解き
年末の最後の数時間をまるで噛みしめるように大事に過ごしている。今年は、一つの原稿に取り掛かっており、とりわけ充実な時間だと感じる。こんどのテーマの一部は、絵解き。絵画伝統の重要な構成をなした数々の活動記録などに思いは馳せつつ、先週、メトロポリタン美術館での鮮明な記憶がときどき蘇る。
このような思いを頭の中で反芻しながら、つぎに目撃した一時は、より意味深い。中国美術の展示室に入り、別の方による中国絵巻についての解説が終わろうとしたところだった。かなりのスペースを割いて展示されているのは、かつてじっくり読み直した「晋文公復国図巻」全巻と「胡笳十八拍図」部分だった。熱心な見学者からは、展示は本物かといういかにも素直な質問が飛び出された。両方とも上質な複製だと見受けられる。しかしながら「よく分からない」との返事だった。どうしてそこで答えを濁らすのか、ちょっぴり不可解だった。
Labels: 展覧会へ行こう
2016年12月26日月曜日
久米仙人の姿
クリスマスが近づくなか、ニューヨークでの休暇を続ける。明るく、温かい日差しを愉しみつつ、広大な中央公園を南北に半分近い距離を歩き、MET(メトロポリタン美術館)に入った。入場料はほぼ日本の国立博物館の倍になることに驚きを覚えながらも、溢れんばかりの訪問客にまじり、館内をゆっくり見てまわった。なにがともあれ、やはり日本関連のものを確かめておきたい。
 絵巻や屏風だけでかなりの空間をもつ大きな展示室を構えている。中でも、りっぱな六曲一双の「徒然草図屏風」(個人蔵)をつくづくと見入った。説明文は、短いながらも、徒然草についての絵画表現の伝統や、ドナルド・キーン氏の翻訳を引用してのエピソード紹介など、あくまでも丁重そのものである。紹介文が触れたのは、つれづれの序段、色欲に惑わされる久米仙人の第八段、それに鼎に頭を突っ込ませた仁和寺法師の第五十三段である。もともと版本の挿絵まで視野に入れれば、徒然草を題材とする画像作はけっして少なくはない。ただ、画題が集中しているわりには、構図において互いの踏襲は意外とすくなく、絵師たちの活発な創作が非常に目立つものである(随筆と絵)。ここの久米仙人は、まさにそれの好例である。仙人の失敗談を描くにあたり、ほとんどの絵は空中に、あるいは地面に落ち転んだ滑稽な格好を競って描くのに対して、目のまえの屏風に見えるのは、あくまでも神様らしく空中に佇む、颯爽とした神様らしい姿である。久米仙人の失敗は、このつぎの瞬間に訪れてくる、ということだろうか。
絵巻や屏風だけでかなりの空間をもつ大きな展示室を構えている。中でも、りっぱな六曲一双の「徒然草図屏風」(個人蔵)をつくづくと見入った。説明文は、短いながらも、徒然草についての絵画表現の伝統や、ドナルド・キーン氏の翻訳を引用してのエピソード紹介など、あくまでも丁重そのものである。紹介文が触れたのは、つれづれの序段、色欲に惑わされる久米仙人の第八段、それに鼎に頭を突っ込ませた仁和寺法師の第五十三段である。もともと版本の挿絵まで視野に入れれば、徒然草を題材とする画像作はけっして少なくはない。ただ、画題が集中しているわりには、構図において互いの踏襲は意外とすくなく、絵師たちの活発な創作が非常に目立つものである(随筆と絵)。ここの久米仙人は、まさにそれの好例である。仙人の失敗談を描くにあたり、ほとんどの絵は空中に、あるいは地面に落ち転んだ滑稽な格好を競って描くのに対して、目のまえの屏風に見えるのは、あくまでも神様らしく空中に佇む、颯爽とした神様らしい姿である。久米仙人の失敗は、このつぎの瞬間に訪れてくる、ということだろうか。
同じ展示室には、さらに伊勢物語、平家物語、南蛮などの屏風が出品されているが、個人的にいちばん思いを馳せる「保元平治合戦図」はついに見かけられない。ただ、同美術館は兜鎧の類の蒐集や展示にかなりの力を入れているらしく、その展示ホールに、日本の甲冑がここでも一室を占めていることを特筆しておきたい。
Labels: 展覧会へ行こう
2016年8月13日土曜日
ドイツ初期銅版画
短い日本訪問が終わり、昨日無事帰宅した。東京にいる最終日には、時間のやりくりをして、上野周辺を歩き、世界遺産ということでずいぶんと話題になった西洋美術館の中に入った。企画展として、メッケネムという、これまでにはまったく知識になかった名前とその作品群を取り上げている。駆け足で見て回った。
 銅版画は、これまで翻訳されたヨーロッパ作品などであれこれと見たことがあって、西洋的なものだという印象をもつ。しかしながら、展示されたものに目を凝らしてみれば、まずはそのサイズが小さいことに意外を覚えた。あえて言えば、平均的にはあの浮世絵の半分以下だろうか。もちろん色は白黒である。西洋絵画を汲み、絵にはたしかに影があるが、それも申し訳程度で、とても写実的な油絵の比較にはならず、見るものには相当な想像力が要求されるものである。展示企画のアプローチとして、聖と俗の対立を打ち出したが、作品の内容からすれば、あきらかに前者のほうが充実している。宗教のエピソードなどは繰り返し表現されたのに対して、世俗を題材にしたものはきわめて数少ない。「挿絵」という言葉はおそらく典型的なヨーロッパの出版様式に属するものであり、それをぴったりと具体化したのは、ほかでもなく銅版画だったという認識を新たにした。
銅版画は、これまで翻訳されたヨーロッパ作品などであれこれと見たことがあって、西洋的なものだという印象をもつ。しかしながら、展示されたものに目を凝らしてみれば、まずはそのサイズが小さいことに意外を覚えた。あえて言えば、平均的にはあの浮世絵の半分以下だろうか。もちろん色は白黒である。西洋絵画を汲み、絵にはたしかに影があるが、それも申し訳程度で、とても写実的な油絵の比較にはならず、見るものには相当な想像力が要求されるものである。展示企画のアプローチとして、聖と俗の対立を打ち出したが、作品の内容からすれば、あきらかに前者のほうが充実している。宗教のエピソードなどは繰り返し表現されたのに対して、世俗を題材にしたものはきわめて数少ない。「挿絵」という言葉はおそらく典型的なヨーロッパの出版様式に属するものであり、それをぴったりと具体化したのは、ほかでもなく銅版画だったという認識を新たにした。
西洋美術館も、おなじく常設展なら写真撮影が可能となっている。常設展のホールでは、多くの人々が携帯電話を絵に向けている。照明は、あくまでも普通形蛍光灯。カメラにはまったく不親切な環境だが、それでも一通り記録を残すためにシャッターを押した。
聖なるもの、俗なるもの
Labels: 展覧会へ行こう
2015年6月14日日曜日
唐の美人
日本、中国への四週間近くの旅行から無事戻ってきた。旅の間にアップロードできなかったエントリーをまとめて出して、関連の書類などを整理したりして、一日でも早く普段のリズムを取り戻そうとしている。
中国西安での旅は、招待側の親切な手配により、歴史古跡の観光も数多く叶えられた。西安といえば、中国に留まらず、世界の文明においてもトップに数えられるもので、歴史的な重みは、いたるところで感じ取れるものだった。紀元前の春秋時代や中国を統一させた秦、そして中華文明の頂点を謳う唐と、どれを取り上げてみても超一流のものだった。一方では、観光となればいずれも陵や墓に終始するのではないかと予想していたのだが、実際はまったくそうではなかった。

墓室の中に立って絵を見つめていれば、周りにはガイドに連れられての観光客は跡を絶たない。ガイドたちはいずれも朗々と説明を続け、しかも同じ内容についてそれぞれ工夫を施して着眼を変えている。中の一人は、目の前の仕女が唐代第一の美人だという評判を下したという日本人の学者の実名を何気なくあげた。観光地のガイドたちの質の高いことに、西安の観光地全般において少なからずに驚き、感心した。
Labels: 展覧会へ行こう
2015年6月12日金曜日
異次元の時空 (5-30)
三週間ほど中国に滞在することになっている。しかもここ数年の似たような旅と違って、今度はちょっぴり遠くへ出かける。今週は、泰山の南にある滕州にやってきた。地元の人々からの大いなるもてなしを受けて、いろいろと見識を広めた。印象に残った場所の一つには、滕州漢画像石館がある。いまなお立て続けに漢の画像石を発見し、まさに現在進行形で漢の画像資料を見つけ出し、発掘した場所で美術館を建てるなど、生きている古代文化の伝承には、さすがにわくわくさせるものがあった。
画像石館で目に入った小さな一点を記しておこう。「水榭垂釣、庖厨」と名付けられた画像の一角には、一釣りで三尾の魚を釣り上げるという幻想的な構図に並んで、魚を調理する様子が描かれている。三つの場面に分かれて、魚を確保したところ、それを籠に収めたところ、そして魚を籠から取り出してまな板に移したところ、まるでアニメに見られる分割された三つの連続した画面のように配置されている。数年前の論文に、絵巻の文法を論じて、その中の一節には「異次元の時空」と述べた。それとはまさに完璧に対応する構図なのだ。いうまでもなく、異次元と呼ぶ理由とは、絵巻の中の物語を伝えると同時に、次元の違う、特定の行動について表現するということにある。その通りだとすれば、ここには物語という次元がないだけに、この称呼は使えないのだろうけど。
漢の画像と鎌倉時代の絵巻、両者の関連性はあまりにも離れている。それにしても、とりわけ中国のことに感心を持つ人なら、やはり親近感を覚えさせるものなのだ。来週の旅先は、西安。絵巻の話をすることになっているので、これをさっそく披露したい。一方では、漢の画像石全般に言えることだが、タイトルはあくまでも現在の研究者が便宜につけたもので、どれも漠然としたものに聞こえてしまう。滕州の美術館でも、館蔵のものについて所蔵品の番号はないのかと訪ねたが、そのような必要性に対しての理解はまったく得られていなかった。いささか残念だと言わざるをえない。
Labels: 展覧会へ行こう
馬と骨 (5-23)
またまた東京にやってきた。今度は学会に参加するためのわずか数日の滞在であり、到着した夜にはすでに予定が入り、翌日からは、自分の発表も含める学会本番の連続だった。そこで、時差対策もかねて、朝の集まりが始まるまでにとにかく歩き回った。ホテルから会場までの距離は四キロ弱、コースを変えて歩いて会場に向かい、じっくり東京の街角の風景を眺めながらの散歩は、それ自体贅沢な休暇だった。

建物の外は、広々とした憩いの場だった。平日の午前という時間なのに、スポーツに打ち込む多数の集合の姿があった。重厚な歴史沈殿の面影をまるで薄めようとする意思が働いているかのように、一瞬感じ取った
Labels: 展覧会へ行こう
2014年5月17日土曜日
キトラの寅
日本の滞在もあっという間に一週間過ぎてしまった。毎日のように行事が続いていても、その合間を縫って出かけてきた。中でも美術館を二つ訪ねた。それもとても対照的になっていて、一つは良いものが展示されていてもほとんど参観者はなく、もう一つは意外なほどの少ない点数の展示品にもかかわらず考えられない人数の観客が集まった。平日の午後にもかかわらず、しっかりと行列を並ばされ、二時間待たされた。

今度の展示の中で、一つのハイライトは壁画の複製陶板とあげなければならない。しっかりした質感と、本物紛いの精密な制作、現物と並べて見られたからこそ、複製ものの完成度をあらためて認識させられ、それの積極的な利用方法をあれこれと想像したくなった。
Labels: 展覧会へ行こう
2013年6月28日金曜日
彫刻の森
ほぼ三十年ぶりに、箱根にある「彫刻の森美術館」を再訪した。前回はたしか雪の中だったが、今度は好天に恵まれた。名高い登山列車は言葉通りの超満員、しかも大多数は年配の方々による観光グループであり、美術館の門前には、修学旅行の若い学生たちが大勢集まり、外国人観光客もかなり目立つ。どうやら「彫刻の森」は相変わらずに老若男女に愛され続けているものだ。

一方では、美術館と呼ぶには、作品の内容や由来についての説明情報は、あまりにも少ない。数多くのロダンの作品などは、ほかの場所で確実に何回も見ている。このレベルの銅像は複数に存在するという事実は分かっているが、これをめぐる常識はまったく持たない。いわゆる複製ではないことはたしかだ。しかしながら、どんなに名作だと言われても、製作当時から十個も二十個も作られたとはとても思えない。そこで、必要に応じて制作されたものは、かなりの時期が経ったので、同じものだと考えるにはどうも違和感を拭えない。展示されている彫刻作品については、工房関連の情報は普通の見学者には提供しないのがいまの基本方針のようだが、その理由など、図りきれない。
彫刻の森美術館
Labels: 展覧会へ行こう
2013年5月31日金曜日
神様の足
「トーハク」で開催中の特別展は、かなりの評判だ。必ず行っておくべきだと数人の知人から教わり、金曜日にはさっそく訪ねた。考えてみれば、ふだんなら神様、信仰という言葉に落ち着くところを、あえて「大神社」と打ち出したものだから、やはりインパクトを感じる。平日の、それも朝早く入館したせいか、予想したほどの人出がなくて、ゆっくりと見て回ることができた。
展示のスケールは、さすがに大きい。このテーマにはすぐ連想される装束、鏡や神輿などはいうまでもない。個人的に関心をもつ絵巻や絵図、古記録もかなりの点数が出品され、丁寧な説明が用意されたこともあって、自然と見学者の群れが出来てしまう。一方では、神像がすごい数に及んで集まったことは、まさに圧巻だった。展示ホールの一つには、ガラスの展示ケース、それも典型的に西洋の彫刻や東洋の陶磁器を展示するものがずらりと並び、
「国宝大神社展」は明日までだ。見逃したら、あとは分厚いカタログを眺めるほかはなかろう。それにしても、電子書籍が流行る昨今、豪華版の展覧会のカタログが一日も早く電子バージョンと並存することを待ち望みたい。
Labels: 展覧会へ行こう
2013年5月19日日曜日
斜めの巻物
さまざまな行事の合間を縫って、できるだけ外を歩き回った。その中で訪ねた一つの展示は、楽しかった。神奈川県立歴史博物館で開催されている「江戸時代かながわの旅-「道中記」の世界-」である。展示内容は、道中記というキーワードで纏められる多様な資料や事象だが、キーワードだけでは伝わりが悪いと判断したのだろうか、地域名が持ち出され、しかもそれを平仮名表記という気の配りようである。はたして学芸員による解説まで設けられ、熱心な見学者がかなり集まった。
江戸の旅は、ポピュラーな話題である。それも周到に用意された展示では、浮世絵や案内地図に止まらず、「浪花講」の帳簿や実際の看板まで展示窓の中に納まったものだから、しっかりと見識を広められた。その中で、やはりまずは巻物に目が行く。中の一点、「東海道行程図」(豊橋市美術博物館蔵)には、大いに興味あった。写真は許されず、その様子を記述するにほかはない。一言で言えば、異様な巻物である。横長に広がっていく料紙は切断されて、その先には、続きの料紙は斜めに繋ぎ合わせて、横へではなく、斜め横へと展開していくものである。巻物に記されたのは地図である。地形の様子をすこしでも現実に近づけて描こうとして、記録媒体そのものをかなり無理な方向へと拵えたものである。このような巻物は、巻き戻したらきっと妙な格好になるものだと、想像するだけでも興味が尽きない。それはともかくとして、この事実は、巻物そのものが日常の一つであり、必要に応じてその様相はいくらでも変えられるという、身近な性格が浮き彫りになったと考えられよう。
写真と触れたので一つ記しておきたい。どうやらたいていの博物館の常設展は、写真撮影を許可する傾向がある。神奈川県立博の場合も、申し出さえすれば、名前も聞かないまま許可の札を渡された。ただし、二次利用はだめだと、はっきりと念を押されたことが印象的だった。
Labels: 展覧会へ行こう
2013年1月26日土曜日
書への視線
いつもながら日本では各地の博物館でさまざまな特別展が開催されているが、それらについてどんなに興味があっても、報道を読んだり、内容などを想像したりするに止めざるをえない。その中で、今週末から始まった東京博物館の特別展は、書聖王羲之を取り上げている。しかも約三週間前に正式発表をした王羲之尺牘(日本語なら「往来」か)「大報帖」の発見が大きく注目を集めた。40年ぶりの、国宝級美術品の発見で、さすがそのインパクトが大きい。

一方では、これだけの発見となれば、海の向こうも熱い眼差しを注いでいる。発見の発表から二週間も経たないうちに、中国では「書法報」においてこれを大きくとりあげ、しかもデジタル時代らしく電子画像だけを利用して、さっそくさらなる推理が展開されている。とりわけ40年前の発見である「妹至帖」を取り出し、両者を電子画像をもって並べて、それが同じ模写を切断されたものだと、書風や内容からだけではなく、紙の模様やその関連まで根拠に用いた。あるいは日本の専門家たちが意識していてもあえて語らなかったことを率直に言い当てたのではないかとも想像するが、デジタル環境下の電子画像の利用例としても、鮮やかでいて、記憶すべきものだ。
Labels: 展覧会へ行こう
2012年3月31日土曜日
二大絵巻を観る
今週の最後の二日は東京で過ごした。デジタル環境の構成に努め、新たな知見を発信しようと真剣に取り組んでいる研究者たちとの交流が叶えられた。その後、これまで論文でしか知らなかった研究者から招待を受けて、待ち望んでいたボストン美術館展を見ることができた。
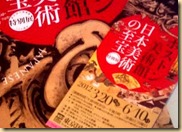
展示の眼目は、いうまでもなく「在外二大絵巻」。「吉備大臣入唐絵巻」も「平治物語絵巻」も、写真や研究書では繰り返し見てきたが、実物はじつはいずれも初めての経験だ。思わず身震いをする思いだった。二つの絵巻とも惜しみなく全巻を広げ、それを隅々までじっくり眺められて、やはりなんとも言いようがない。絵巻とは手の中の映画だという、あの有名な着眼に反論を抱き、見る人の気持ちと都合でいくらでも見れるものだとの小さな持論をことあるごとに披露している自分だが、しかしながらこの時だけはまったく違う体験をさせられた。人ごみに押され、後ろで待っている人々から反感を買わないようにと、決まったペースで前へと移動せざるを得ない。その結果、世紀の絵巻はまさに目の前を流れていく映画のようなものだった。もともとこのような見方でも新たな発見は多い。吉備を招く宮殿の前に設けられた虎の皮が敷かれた座席、平治の戦火の中で牛車の車輪に轢かれた男など、なぜかとても印象に残った。そして、あのあまりにもアンバランスな奥書。
ボストン美術館の公式サイトでは、「吉備大臣入唐絵巻」のほとんどの場面を、サイズは小さいが綺麗なデジタル画像で公開している。そこで改めてタイトルの英訳を見つめた。「Minister Kibi's Adventures in China」。これをこのまま日本語に直すと、さしずめ「内閣大臣キビの中国アドベンチャー」といったところだ。官位の「大臣」はやむなしとしても、「行く」ことが「冒険」と意訳された。いうまでもなくさほど予備知識を持たない英語の読者には、こちらのほうが伝わりやすいに違いない。
Labels: 展覧会へ行こう


