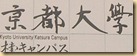オンラインの地図、たとえばグーグルマップを愛用している。いまはその使い勝手など、並のカーナビと比べてもまったく引けを取らない。それに歩行用のモードにして、経路や距離などを出したら、たとえただたんに眺めていても興味がつきない。さらに言えば、歩行用のナビゲーションに頼り過ぎたら、歩くための大事な感性が退化するのではないかと心配までするものだが、地図を画像として保存して小さな画面で時々確かめるだけなら、小道に迷い込んだときのスリリングまで味わえられて、まさに文句がない。
そこで、ついつい地図そのものの出来栄え、あるいはデータのあり方まで注意を払うようになる。たとえば週末には竹藪の中を潜って、苔寺まで歩いてみた。目的地までの三つのお寺をめぐるグーグルマップの情報は、まさに対象的なものだった。歩いてまず足を止めたのは、黄檗山末寺の浄住院。奥深い境内の中に入って周りを眺め、それが手元の地図にはまったく載っていないことに驚いた。つぎに訪ねたのは、地蔵院。こちらは拝観料を支払わなければ入れないような観光スポットになっているにもかかわらず、地図は道路からかなり離れた奥地として載せていうる。いよいよ苔寺に近づいて、すぐ近くには鈴虫寺。駐車場には数人の交通整理の警備員が忙しく働いているぐらいの繁盛ぶりで、狭い山門の奥はごったがえしていて、まるでにぎやかな喫茶店の待合スペースに化して、そそくさに退散した。戻って、パソコンの前に座り、あらためてオンラインで確かめてみざるをえない。浄住寺の情報はたしかに収録されている。ただし、さらに二つレベルにズームインしてからでないと、それが現われてこない。念のために、Bingの地図で調べると、浄住寺も
ここに昼過ぎの日差しに包まれた浄住寺の写真を一枚添えよう。この静けさは、あるいは地図にまで距離を置いたこととまったっく無関係でもないのかもしれない。

 し登場した「日本」は、一つの奇妙な風景をなす。それが意味するところは、ほぼ二つのグループと分かれる。一つは、「日本国をあわせて戦ふとも」、「日本六十余州」などのように、天下すべてとの思いを込めた、世の中を指し示す。「州」の数を定かなものにしない漠然さは、むしろ果てしない「日本」を際立たせるレトリックになる。もう一つは、震旦、天竺に対するものではなくて、竜宮に相対するものとして持ち出される。想像を絶する竜宮の饗宴を前にして、秀郷の思いと言えば、「酒宴の儀式、日本には様変はりて」と結論しておいて、その特異性を並べ立てた。ここに見る「日本」は、ほかならず神仙境に相対する人間の世を意味するものだった。
し登場した「日本」は、一つの奇妙な風景をなす。それが意味するところは、ほぼ二つのグループと分かれる。一つは、「日本国をあわせて戦ふとも」、「日本六十余州」などのように、天下すべてとの思いを込めた、世の中を指し示す。「州」の数を定かなものにしない漠然さは、むしろ果てしない「日本」を際立たせるレトリックになる。もう一つは、震旦、天竺に対するものではなくて、竜宮に相対するものとして持ち出される。想像を絶する竜宮の饗宴を前にして、秀郷の思いと言えば、「酒宴の儀式、日本には様変はりて」と結論しておいて、その特異性を並べ立てた。ここに見る「日本」は、ほかならず神仙境に相対する人間の世を意味するものだった。
 ところで、「コーパス」とは、体だ。しかもオランダには「コーパス博物館」と名乗るものが存在していると聞く。もともとこちらのほうは、子供たちのための遊園地、ということがコンセプトで、中身は人間の体を巨大に作って、生身の人間をその中を回遊させるという知的なファンタジーランドだ。これに照らして言えば、言語学などにみる「コーパス」とは、体というよりも、体のパーツといったところだろう。体を分解させておいて、それをもって得体の知れない体に対する新たな発見を、というのがそもそもの希望だったかもしれない。
ところで、「コーパス」とは、体だ。しかもオランダには「コーパス博物館」と名乗るものが存在していると聞く。もともとこちらのほうは、子供たちのための遊園地、ということがコンセプトで、中身は人間の体を巨大に作って、生身の人間をその中を回遊させるという知的なファンタジーランドだ。これに照らして言えば、言語学などにみる「コーパス」とは、体というよりも、体のパーツといったところだろう。体を分解させておいて、それをもって得体の知れない体に対する新たな発見を、というのがそもそもの希望だったかもしれない。